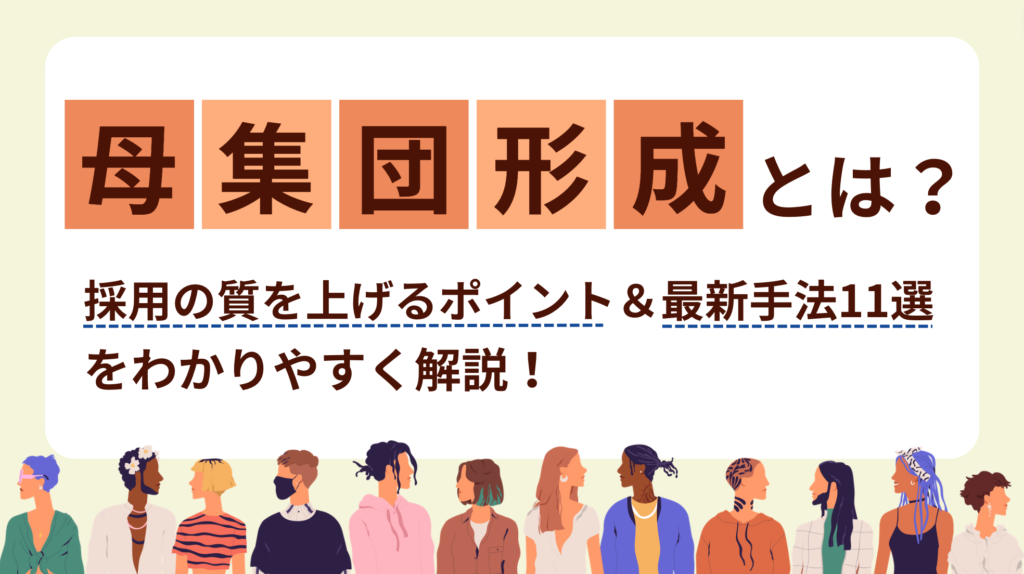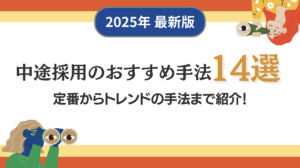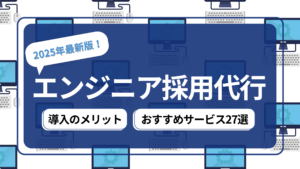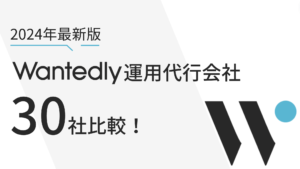近年、「転職」自体は当たり前になっていますが、そもそも労働人口が減少していたり、どの企業もあの手この手で採用を強化していることから、年々人材採用は困難になっています。
特に、募集者を集める「母集団形成」において、課題を抱えているという声を聞くことが非常に多いです。母集団形成は、採用プロセスの基本段階なので極めて重要である一方「具体的にどのような施策をしたらいいか」という部分に関してはあまりノウハウが出回っていません。
そこでこの記事では、採用における「母集団形成」の特徴やポイント、手法別の特徴や新卒採用と中途採用での違いについて網羅的にご紹介します。
\採用課題は「即戦力RPO」にご相談ください/

独自に収集した20万件以上のデータを元に
320社以上の採用を支援
採用戦略設計・採用媒体のアルゴリズムハック・スカウト業務・人材紹介会社の統括・採用広報など、貴社のニーズに合わせてあらゆるソリューションを全て高品質で提供します。
採用課題は
\「即戦力RPO」にご相談ください/

独自に収集した20万件以上のデータを元に
320社以上の採用を支援
採用戦略設計・採用媒体のアルゴリズムハック・スカウト業務・人材紹介会社の統括・採用広報など、貴社のニーズに合わせてあらゆるソリューションを全て高品質で提供します。
母集団形成とは?
「母集団形成」とは、企業が求める人材像に合う候補者のグループ(集団)を作り上げるプロセスを指します。この用語は、もともと統計学の概念で、全体の対象集団を表す言葉です。
採用活動の中では「応募者プール」とも言われることもあります。
しかし、ただ単に候補者数を増やすだけでなく、企業に興味を持っており、かつ求める人物像とマッチする候補者を集めることが重要です。つまり、「母集団形成」は量と質の両面で考えるべき項目なのです。
そもそも「母集団」とは何なのか?
採用における母集団とは=「自社にポジティブなアクションを起こした人物の集団」です。そして母集団形成は、「自社に興味を持っている人材を集める活動」の全体を包括的に指す言葉です。
母集団とは、以下のような行動をした人々が含まれます。
- 新卒採用でプレエントリーの登録をした
- 自社のブログ記事に「いいね」をつけた
- 採用イベントや企業説明会に参加した
- 実際に求人に応募をした
- ダイレクトメッセージ(スカウトメール)に前向きな返信をした
多くの採用担当者は、「確実に”応募”というアクションをとった候補者」を母集団として重視する傾向がありますが、プレエントリーやイベントへの参加も、自社への興味を表す行動として十分な要素なので「母集団」としてカウントすることをおすすめします。なぜなら、この段階でもメールアドレスや電話番号などの個人情報を得ることができており、採用担当者側からも積極的なアプローチをすることが可能だからです。
例えば、プレエントリー段階の候補者でも、本エントリーまでの導線設計をしっかりと行うことで正式な応募までつなげることができれば、結果的に効率良く大きな母集団を形成することができます。母集団形成に課題を感じる人事担当者様は、応募を待つのではなく、自社にアクションを起こしてくれた候補者を母集団として認識し、積極的に本エントリーや選考段階に進めるアプローチを行いましょう。
採用活動において母集団形成はなぜ重要なのか
母集団形成の重要性は、大きく2つに分けることができます。
1つ目は、少子高齢化に伴う労働人口の減少です。この状況により、企業間で候補者を取り合う採用競争が激しくなり、求職者の確保がますます難しくなっています。この状況を打破するために、より母集団形成が必要とされています。
2つ目は、企業間で採用ターゲットが重複していることです。これには、大手企業が新卒採用だけでなく中途採用も増やしているという背景があります。優秀な候補者は、より知名度や待遇の良い大手企業に引かれる傾向があるため、中小企業やベンチャー企業が採用市場において人材獲得に苦労しているのです。
上記2点から、企業が人材を確保することが難しくなっているため、企業は常に自社に興味のある人材を集め(=母集団形成)、採用活動を行う必要があるのです。
母集団形成のメリット
母集団形成を戦略的に行うメリットは、大きく分けて以下の4つです。
- 計画的に採用活動ができる
- 採用コスト最小限に抑えられる
- 入社後のミスマッチと離職率を下げることができる
- 自社の生産性向上や事業の成長につながる
それぞれ、次の項目で詳しく解説していきます。
メリット①計画的に採用活動ができる
母集団形成を意識することで、計画的に採用活動を行うことができます。実際、最終的に目標とする採用人数をもとに、過去の選考通過率などを利用しながら必要な母集団の人数を見積もることができ、細かなKPIを立てやすくなります。
すると、母集団形成の時点で目標値に達していない場合に目標を見直したり、採用戦略/戦術を見直したりなどのアクションをとることができます。このように、早い段階で課題に対応できるため、計画的に採用活動が行えるのです。
メリット②採用コストを最小限に抑えられる
母集団形成には、採用コストを最小限に抑えられるというメリットもあります。例えば、ターゲットを確定せずに次々に内定を発行してしまうと、想像を超える社員が入社し、採用コスト/人件費が当初の予算を超えてしまう可能性があります。逆に、母集団形成の時点で目標人数より少なく、採用人数に達しない場合、追加の採用プロセス(二次募集、三次募集など)が必要となり、時間的にも金銭的にも余計なリソースが発生してしまいます。
母集団形成を行うことで、目標の採用人数に基づいて適切な採用手法を検討しやすくなり、それに合った最も効率の良い採用戦略を立てることができるのです。
メリット③入社後のミスマッチと離職率を下げることができる
母集団形成で、採用後のミスマッチを防ぎ、社員の定着率を向上させることも期待できます。理由は、母集団形成の段階で自社へのマッチ度の高い、いわゆる「有効な人材」を事前に集めておくことで、入社後のギャップを減らすことができるからです。入社前後のミスマッチを防ぐことができると、必然的に社員の定着率も向上します。
メリット④自社の生産性向上や事業の成長につながる
前述したように自社にマッチしている人材で母集団形成ができると、将来的に自社で活躍(=成功)する可能性の高い人材を採用することができ、長い目で見た時に、圧倒的に自社の生産性向上や成長に繋がります。
採用の質を上げる母集団形成のプロセス7選
ここからは、効率良く質の良い母集団形成を行うためのポイントを採用のフローに沿って7つご紹介します。
- 他部署と連携して採用目的を明確にする
- 採用ターゲットを決める
- 採用目標を決定する
- 採用戦略を設計する
- ターゲットに合わせたアプローチ手法を選択する
- 候補者を引き寄せるコンテンツを作成する
- 課題点を洗いだし、改善する
①他部署と連携して採用目的を明確にする
まずは、採用の目的を明確に定めることが重要です。採用の目的を共通認識として現場の人とすり合わせながら設定することによって、最終的に質の良い採用が行えるようになります。
「そもそも、採用の目的が何なのか」という部分だと欠員がでて穴埋めが必要なのか、企業の未来や発展のために新しいメンバーを募集するのか、そういった背景によっても適切な採用手法が変わってきます。
たとえば、「若手人材が不足している」「将来のリーダーを育てたい」「なるべくコストをかけずにリソースを確保したい」といった要望がある場合には、新卒採用や業務委託が最適です。
一方で、「急な欠員が生じ、即戦力が必要」「高度な専門スキルやノウハウを持つ人材が必要」という場合には、中途採用やハイクラス人材の業務委託が適しています。
現在の組織の人材状況を把握するためには、人事や採用担当だけではなく現場の人にも意見を求め、自社に必要な人的リソースを抽出し、それに該当する人材がどの部署にどれだけ存在するかを整理しましょう。これにより、自社に不足している人材の特徴が浮かび上がり、次のステップである採用要件の設定がしやすくなります。
②採用ターゲットを決める
母集団形成の鍵は、採用ターゲット(人材要件)を明確に定めることです。採用ターゲットを明確に設定することによって、より採用ターゲット合った採用戦略を設計することができ、最終的に質の良い母集団を形成することができます。
採用ターゲットの決定には、以下のように2つの方法があります。
- 未来の事業や組織の展望をもとに逆算して定義する「演繹的アプローチ」
- 既に成功している人材をベースに定義する「帰納的アプローチ」
です。詳細な設定方法については、関連記事で解説されていますので、参考にしてください。
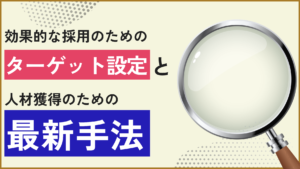
また、採用目的のプロセスと同様、採用ターゲットの設定にも現場へのヒアリングが重要です。採用担当者や経営者からの客観的なイメージだけではなく、日常業務のリアルな実務状況や感覚をヒアリングすることによって、より自社に業務内容にマッチする採用ターゲットを設定することができます。
採用ターゲットを適切に設計することによって、候補者にアプローチする際に的を得た施策を実施することができ、より質の良い応募を集める(=母集団形成をする)ことができます。
③採用予定人数を設定する
次の母集団形成のステップとして、採用予定人数の設定が不可欠です。採用予定数を決定するには、以下の5つの要素を検討します。
- 会社の事業計画
- 自社の人員構成
- 過去の採用実績
- 現場からのニーズ
- 採用期限からの逆算
新規プロジェクトや事業計画に基づいて、将来的に必要な人材の数を予測し、それに応じて採用予定数を設定します。人員構成は年齢、雇用形態、職種などで整理し、採用期限も見据えた上で現実的な採用人数目標を設定しましょう。
現場の具体的なニーズと経営側の要件をヒアリングすることで、採用予定数のバランスを取ることが重要です。これにより、母集団形成をした後の絞り込みの段階においても過不足ない採用活動を行うことができます。
④採用戦略を設計する
適切な母集団形成と最終的な採用目標の達成のために、最終的なゴール地点から逆算した採用戦略設計が必要です。
特に新卒採用では、各企業が同時期に採用活動を開始するため、競合他社に先駆けて優れた人材を確保するためにも、スケジュールの遅れや採用活動中の停滞は命取りになります。
中途採用の場合も、人員補充や新プロジェクトの開始に伴う採用など、目的に応じて採用時期を設定します。新卒採用に比べて採用までの期間は短い場合もありますが、関連部署との調整が必要な場合もあるため、余裕をもったスケジューリングが必要です。
⑤ターゲットに合わせたアプローチ手法を選択する
母集団形成の手法を選定する際には、自社の採用要件やターゲットに合わせた適切な手法を選択する必要があります。
採用したい職種や雇用形態、年齢、新卒か中途採用かなどの要素を踏まえ、それに最も適切な採用手法を選択します。また、一口に採用媒体といっても得意とするポジションや特徴が異なるため、自社のニーズやリソース、予算にマッチするような手法やツールを選ぶようにしましょう。
⑥採用ターゲットに刺さるコンテンツを作成する
アプローチ手法が決まったら、次は「採用ターゲットに刺さるコンテンツ」を作成します。どの手法にも当てはまる求人作成や、イベント運営なら企画の立案、スカウトならスカウト文章の作成が必要になります。
どのコンテンツ作成においても、1番重要なのが「採用ターゲットにだけ刺さること」です。保険をかけて他のターゲットにも刺さるような広い訴求にしてしまうと、肝心な採用ターゲットにはイマイチ興味を持ってもらえないコンテンツになってしまいます。
どのコンテンツにおいても「魅せ方」が重要なので、採用ターゲットの立場になった上で「どんな文言だと惹かれるのか」「どんなクリエイティブだと応募したくなるのか」などを研究しましょう。
⑦結果を分析して次の施策を行う
コンテンツを作成して、母集団形成の施策を実行したらそれで終わりではありません。それぞれの施策に対して出た結果を分析し、新たな施策を考える必要があります。
施策に対しての反応があまり良くなかった場合はもちろん原因を分析して改善施策を実行しますが、施策が当たった場合も集まった母集団に対してフォローを行う必要があります。採用活動全体の質を底上げするためにも集まった母集団の自社に対する志望度やポジションに合わせて正式な応募につながるフォローアップ施策を行いましょう。
母集団形成の手法11選
それでは、実際にどのような母集団形成の方法があるのか、下記11個の採用手法を、特徴やポイントなどを合わせてご紹介します。
- 求人媒体(求人広告)
- 人材紹介サービス(エージェント)
- 採用広報用のHP作成
- 採用イベント
- スカウト採用(ダイレクトリクルーティング)
- リファラル採用
- SNSの運用
- 自社広告の運用
- ハローワーク
- ミートアップ/交流会
- 学内説明会
①求人媒体(求人広告)
採用媒体の主な特徴は以下の通りです。
- ターゲット層の幅が広い。(媒体によって異なる)
- 費用はおおよそ10~100万円程度で、自社の予算に合わせて選ぶことができる
- 複数のプランから選択可能。
これは、求人媒体やハローワークなどの情報誌などを利用する方法で、幅広いターゲット層にリーチすることができるのが特徴です。費用には成果課金制と前払い制、従量課金制の3つの方法があり、プランや媒体、掲載期間によって相場が異なります。
一度の掲載で多くの応募を獲得できることがメリットですが、前払い制の場合、応募がない場合でも費用が発生してしまうというデメリットもあります。
求人媒体には古典的な新聞やフリーペーパー、求人サイトなどが存在し、エリアや業種に特化したもの、年齢別にターゲットを絞るものなど、同じ媒体でも異なる特徴を持つツールがあるので、自社の採用ターゲットに合わせてうまく選定する必要があります。
②人材紹介サービス(エージェント)
人材紹介サービスの主な特徴は以下の通りです。
- ターゲットの要件を詳細に設定することができる。
- 成果報酬のケースが多く、リスクが少ない。
- 非公開の求人でも採用できる。
人材紹介サービスは、ピンポイントで欲しい人材を人材紹介会社が見つけるサービスです。主な特徴は、ターゲットの要件を詳細に設定できることと、人材紹介会社が人材の質を担保してくれることです。
人材紹介会社のノウハウと信頼性により、通常の求人では見つけにくい人材に出会えることもあり、特に専門職やハイクラス人材の採用に役立ちます。また、非公開の求人で応募を集めることも可能です。
一方で、仲介手数料として一般的に理論年収の30%〜40%を支払う必要があり、採用費用単価が他の方法よりも高いのがデメリットです。そのため、広く浅い母集団形成ではなく、特に狭く深い母集団形成に有効です。
③採用広報用のHP作成
採用(広報)ホームページの主な特徴は以下の通りです。
- 人材の定着に寄与しやすい。
- 長期的に利用可能。
- 成果が出るまでに時間がかかる。
採用ホームページは、採用ターゲットに焦点を当てたウェブサイトで、候補者からの興味度を高め、応募を獲得する手法です。写真や映像などを駆使することにより、自社の魅力を最大限に伝えることができるという利点があります。
社員インタビューなどで採用後の働き方やキャリア形成についてもアピールできるため、興味を引くことができれば、大きな母集団を形成することができます。また、他の方法とは異なり、ウェブサイトを慎重に構築すれば、長期間にわたって活用することが可能です。しかし、デメリットとして、応募などの目にみえる成果をが出るまでには時間がかかることがあります。
十分な知名度がない場合、ホームページを制作してもそこに流入する数が少なく、応募が急激に増えることは難しいため、求人検索エンジンと連動させたり広告を回すなどの工夫が必要です。
④採用イベント
採用関連イベントの主な特徴は以下の通りです。
- 幅広い対象層にアプローチすることが可能。
- 主に新卒採用において有効。
- 成果にかかわらず様々なコストが発生する。
採用説明会などのイベントでは、広範な人材に企業の魅力を伝える機会が提供されます。これは自社で開催できますが、公的機関や学校でのイベントに参加することで、同じ年齢層のターゲットに一括してアプローチできるというメリットがあり、主に新卒採用に活用されます。
また、エンジニアにおいては「勉強会」を開催することで、定期的な接触回数を増やすことができるため、積極的な開催をおすすめします。
⑤スカウト採用(ダイレクトリクルーティング)
スカウト採用(ダイレクトリクルーティング)の主な特徴は以下の通りです。
- ターゲットの要件を詳細に設定可能。
- 求職者に直接接触できる。
- 1人の採用者に対する労力が比較的多い。
スカウト採用は、企業が直接求職者にアプローチできる採用方法です。通常の採用手法とは異なり、人材紹介会社や求人を介さずに、求職者が登録したデータベースを通じて直接スカウトを行います。
企業は自発的にアクションを起こすことができ、的確な人材に自社の魅力を伝えるメリットがあります。ただし、採用にはデータベースの検索、スカウトメッセージの作成、応募対応など、多くのリソースが必要です。
そのため、大量の採用を行う際には向いておらず、少数かつピンポイントでアプローチしたい場合に効果的です。
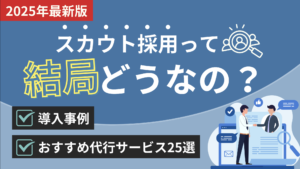
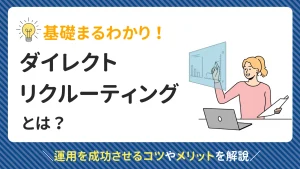
⑥リファラル採用
リファラル採用の主な特徴は次の通りです。
- 採用コストが低い
- 自社にマッチする候補者を獲得しやすい
- 大量採用には向いていない
リファラル採用は、自社の社員が新たな候補者を推薦する手法です。この方法は、通常の採用方法に比べてコストがかからないという大きなメリットがあります。一部の企業では従業員に報酬を支払う場合もありますが、それでも他の採用方法に比べると非常に安価です。また、自社の事情をよく理解した従業員がスカウトを行うため、適切な候補者を採用しやすいことが特長です。
ただし、大量の候補者を採用したい場合には向いていません。 そのため、他の採用方法と組み合わせて「運がよければ採用できる」という温度感で使用しましょう。
⑦SNSの運用
SNSを活用した採用の主な特徴は以下の通りです。
- 幅広いターゲット層にリーチできる
- 広告出稿には費用がかかる
- 運用には時間、スキル、リテラシーが必要
SNS運用による採用活動は、コストを削減できるというメリットがあります。有料のSNS広告にはコストがかかることもありますが、ターゲットの特性に合わせて配信できるため、高い費用対効果が期待できます。
また、自社のアカウントを介して柔軟に情報を発信できるため、求職者とフランクなコミュニケーションができ、ファン化にもつながりやすいです。また、最近ではSNSプラットフォームだけでなく、動画共有サイトに公式チャンネルを設ける企業も増えており、さまざまな発信方法があります。
しかし、応募者を確保するには多くのフォロワーや登録者を獲得する必要があり、結果を出すためには時間と知識が必要です。また、SNSは企業の評判に直接的に影響を与える可能性があるため、1つ1つの発言に注意が必要です。
SNSを利用した詳しい母集団形成の方法についてか以下の記事も合わせてご覧ください。

⑧自社広告の運用
自社で広告を運用する特徴は以下の通りです。
- ターゲットに合わせて媒体を自由に調整することができる
- 潜在層にもアプローチできる
- 運用スキルによって施策の効果が大きく変わる
自社で広告を回すことは、企業が採用LPを幅広く世間全体に届けられる施策です。新卒や第二新卒、大企業の営業職など多くの人材に一気にアプローチしたい場合に有効です。また、Googleやメタ(facebook/instagram)、TikTokなど自社のターゲットや予算に合わせて媒体を選定することができるのも特徴の一つです。
ただ、一定の広告運用スキルを必要とし、広告運用知見がない場合はコストを大幅に無駄使いしてしまう可能性があるため、既に自社にマーケターがいる場合や広告代理店と契約している企業向けの施策になります。
⑨ハローワーク
ハローワークを利用する特徴は以下の通りです。
- 厚生労働省が設置している公的機関なので掲載が無料
- 幅広い年代や職歴の人に見てもらえる
- 正式な手続きまでに工数がかかる
ハローワークは厚生労働省が運営している公的期間であり、全国各所にあります。無料で掲載できるため、母集団形成にコストをかけたくない方にはおすすめですが「質の良い母集団」という点を重視する上ではアプローチするターゲットを選べないので少し不向きです。
ただ、学歴/経歴/年齢を問わない工場作業員や清掃スタッフ、コールセンターや地元密着型の企業にはおすすめです。
⑩ミートアップ/交流会
ミートアップ/交流会の特徴は以下の通りです。
- 自由なテーマで開催できる
- 潜在層にも直接接触することができる
- 定期開催にすると企画工数がかからず、仕組み化できる
ミートアップや交流会はいわゆる「企業説明会」とは異なり、一般的に「採用」というワードは表に出しません。エンジニアの勉強会やマーケターの交流会と称して開催し、最後の参加者アンケートで自社のカジュアル面談に誘導します。
イベントの企画が良い場合は自社の良いブランディングになるので、イベント内でファン化させることができ、意外と有効な母集団を形成することができます。
⑪学内説明会
新卒採用での母集団形成において意外と穴場なのが「学内説明会」です。自社のターゲットとする学生がいる大学もしくは専門学校などに向けて「自社の説明/魅力訴求/学生に対してのメリット」などを記載した上で連絡をし、イベントを開催しましょう。
大規模なものである必要はなく、オンラインなどで1時間の開催でも十分です。
実際にあった事例だと、某金融系ベンチャー企業がビジネスコンテストで多数受賞歴のあるゼミにイベントを開催し、1回で優秀層の学生30名の母集団形成を行なったこともあります。
採用職種別の母集団形成のポイント
次に、新卒採用と中途採用それぞれにおける母集団形成でのポイントをご紹介します。
新卒採用
学事日程に合わせて計画を策定する
経団連が「就活ルール」を廃止した結果、新卒採用の競争状況は非常に変動的となりました。しかし、新卒採用はあくまでも学生をターゲットにしているため、基本的には学事日程を考慮してスケジュールを設定する必要があります。内定発表から逆算して、面接や応募の時期を計画的に設定しましょう。
幅広い学生と交流を深める
新卒採用では、応募者の業務経験やスキルよりも、個人の魅力や意欲を評価する傾向が強いです。したがって、まずは多くの学生と接点を持つことが重要です。自社に適した候補者を見極めるために、幅広い学生と交流を深め、潜在的に自社にマッチする人材を見つけ出すことが求められます。
中途採用
求人要件に適したターゲット像を明確にする
中途採用のプロセスでは、特定の職種やポジションに関連する具体的な要件を明確にし、候補者の経験、スキル、知識などを総合的に評価することが重要です。ただし、これだけに固執せず、より良い採用を実現するためには、自社が求める理想的な人物像を定義し、採用候補者がそれに合致するかどうかを評価することが必要です。中途採用の際には、求める人材像を明確にし、マッチする候補者を探す際の基準として活用しましょう。
共通
具体的なターゲットを設定する
「求める人物像とのミスマッチを避けるために、事前に人事や関連部門と協力し、募集ポジションの具体的な採用ターゲットを設定しましょう。これによって、不適切な応募を減らすことができ、有効な母集団を形成できるだけでなく、社内でターゲット像を共有することで、より満足度の高い採用活動を実現できます。
ターゲットにとって魅力的な内容を発信する
ターゲットを具体化したら、その層を引きつけるための効果的な訴求を発信することに注力しましょう。採用担当者だけでなく、社内のスタッフからのフィードバックを収集し、自社の強みに関する共通の理解を得ることも重要です。
複数の手法を組み合わせて母集団を形成する
母集団形成にはいくつかのアプローチ方法があり、それぞれに長所と短所が存在します。そのため、お互いに補完し合える方法を複数組み合わせることが重要です。採用ポジション、コスト、スケジュールなどに合わせて最適な組み合わせを考慮しましょう。
採用データの収集と分析
採用においてデータ収集、整理、分析は非常に重要です。例えば、異なる手法ごとの成果を評価することも重要です。各応募チャネルごとの応募者数、各段階の進行状況、辞退者数、内定者数、コストなど、収集できるデータは多岐にわたります。これらの情報を収集し、数値を分析することで採用活動の効率を向上させることができます。
幅広い情報収集
働き方や価値観の多様化に伴い、働き方のトレンドは常に変化しています。そのため、自社の領域の人材動向や、競合他社の状況など、広範な情報を収集する必要があります。外部の人材サービス企業などとも積極的に情報共有を行い、効率良く情報を集めましょう。
まとめ
今回は、母集団形成の重要性に焦点を当て、戦略的かつ計画的な採用活動について説明しました。有効な母集団を形成することができれば、優れた人材や自社のニーズに合致する人材を格段に獲得しやすくなります。
特に中途採用の場合、今までのように経験やスキルに重点を置いて採用を進めることは、ますます大手企業や知名度の高い企業へ人材が流れてしまう原因になります。
自社に適した母集団とは何か、どのような人材を求めているのか、どのような手法を使えば効率よく安定的に母集団を形成できるのかを明確にし採用活動に取り組みましょう。
以下の記事でも、母集団形成について解説しています。ぜひご参考にしてください。
しゅふJOB「母集団形成」を増やし採用を成功させる方法・手段まとめ」
母集団形成なら「即戦力RPO」
弊社、株式会社ミギナナメウエが運営している「即戦力RPO」は採用支援サービスですが、媒体のアルゴリズムハックを行ってどんな企業でも募集記事を上位表示させることができるなど、あらゆるノウハウを保有しています。
- 中途採用をしたいけど、知名度がなくて応募が集まらない
- 母集団形成の方法がイマイチ良くわからない
- 採用を強化させたいけどリソースが足りない
などのお悩みをお持ちのご担当者様は、ぜひ無料相談にてご相談ください。